ジュラシックワールドと自分の人生
はじめに
昨日、ジュラシック・ワールドを見に行こうと思い立った。
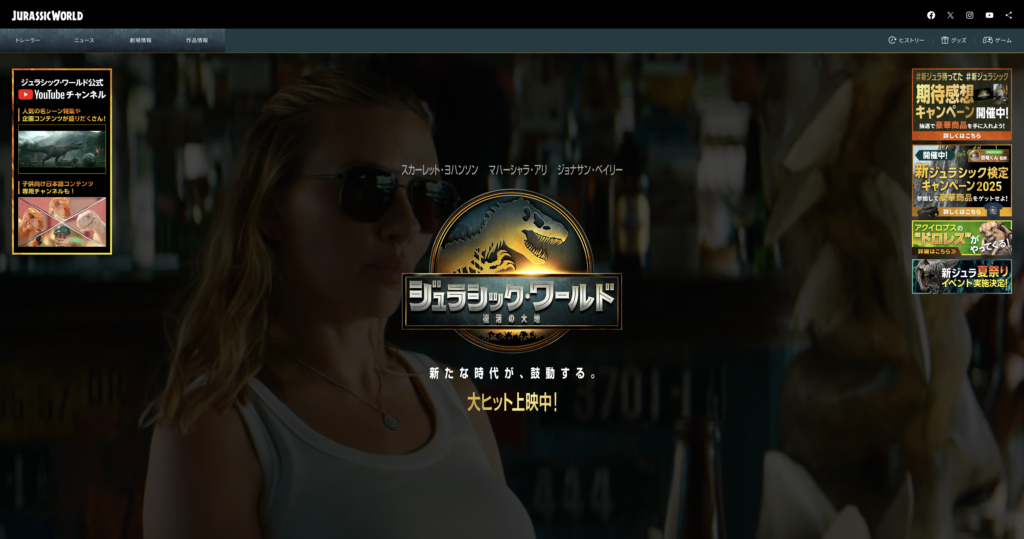
奇遇にも誕生年が同じ
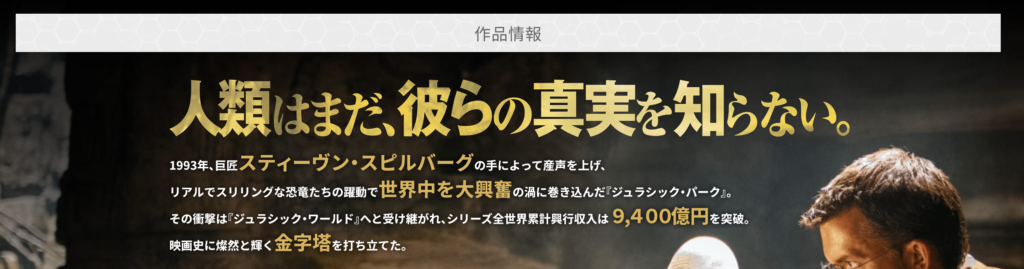
巨匠スィーヴン・スピルバーグがジュラシック・パークを生み出したのは、1993年。
私の誕生年と同じ。
これも何かの縁である。
パークからワールド
パークからワールドという流れが想起される。
規模が拡大している。
鼓動とスピーカーの臨場感
トヨタシンフォニービルのスクリーン8で、映画『ジュラシック・ワールド』を観た。
ティラノサウルスの鳴き声が、鼓動というスピーカーを通して伝わってくる臨場感がすごかった。
「鼓動」といえば、万博のフランス館にあったインスタレーションを思い出す。

生き物の鼓動のダイナミックさ、それを今後も感じていきたいと思った。
隣の席の人とのやりとりとドリンクの置き場所
自分の席の右か左側どちらに購入したペットボトルの水を置くかどうかで悩んでいたところ、「置いて大丈夫ですよw」と、声をかけられた。
自分としては、右と左どちらに置こうか、迷っていただけだった。
自分が映画の席の設計者だったら、左か右どちらかに座席の番号を書いておくだろう。
しかし、反対側に飲み物を置いた人がいたら、ルールを破ったということになってしまうから、両方どちらに置いても良いとするのが、社会全体のことを考えたら最適なのかもしれない。
危険を冒してでも見たい景色
映画の中で、陸上の恐竜が群れをなして暮らす地にたどり着くシーンがあった。
その完成度は圧巻で、実物の恐竜を見たことのない博士が、思わず歓喜の声をあげていた。
あの瞬間の博士のように、私も日常の中で、心の底から歓声をあげられるような瞬間を味わいたい。
普段は上司や同僚への報告・連絡・相談(ほうれんそう)をためらってしまうことがあるが、もし映画の恐竜学者のように歓喜を味わいたいなら、ある程度は自分にとってのリスクを取る必要がある。
映画のミッションでは、陸・海・空の恐竜の遺伝子を採取し、人間の寿命を20年延ばすことが目的だったが、その過程で2人の命が奪われた。
自分の場合、命を失うリスクはない。だからこそ、最悪のリスクを想定した上で、自分が見たい景色にたどり着くための挑戦は積極的にしていきたい。
まだ人生、そして仕事の冒険は続いていく。
恐ろしさとの対比
危険の中にも可愛らしさがあり、特に途中で出てきた子供の恐竜はとても可愛く、恐ろしさとの対比が際立っていた。
究極の選択
物語の中では、「1人を救うか、全員を救うか」という選択が突きつけられる思考実験のような描写があった。
目の前の1人を助ければ、その人は助かるが全体は危険になる——そんな状況で助けない選択をする人物も描かれていた。
地球規模での視点
恐竜は約2億年、地球で生きたが、自然現象によって絶滅した。
人類の歴史はその10分の1以下しかなく、人間もいつかは恐竜と同じ運命を辿るだろう。
熊のニュースもあったように、人間は地球の中心ではなく、その一部にすぎない。自然破壊を繰り返せば、絶滅は早まるかもしれない。
また、人間以外の生き物を観察することで、人間社会の小さな悩みにとらわれず、地球規模で物事を考えられるようになる。
視野が広がれば、物事を多角的に捉えられ、問題の解像度が上がったり、ゴールへの最短ルートも見えやすくなる。
ジュラシックワールドの世界が美しい
恐竜のような巨大生物や広大な景色を映像で見せられると、とても美しいと感じた。
旅行に行って、外の景色に意識を向けているときの感覚に近い。
観察と畏敬によって、これからも地球の美しさを言葉にしていきたいと思う。
3つに絞り込む
今回の映画でミッションの対象になった恐竜は、陸・空・海の3種類。
「人間の認知の限界は3つ程度」という説もあり、映画の進行がわかりやすく、長く感じなかった。
これを仕事に応用するなら、大きな目標を小さく区切り、3つ程度のサブゴールを設定すると進捗が伝わりやすくなる。
オープンソースかどうか
無事、人間の寿命を20年延ばすという新薬に必要な3つの恐竜のDNAを採取できていた。
プログラミングの世界で言われているようなオープンソースにしてみては?
という描写があった。
それでは金にならないよ。
と、否定されていた。
そのやりとりを踏まえると、プログラミングの世界のオープンソースは非常にありがたい。
ホリエモンが言うように、なんだってできる。
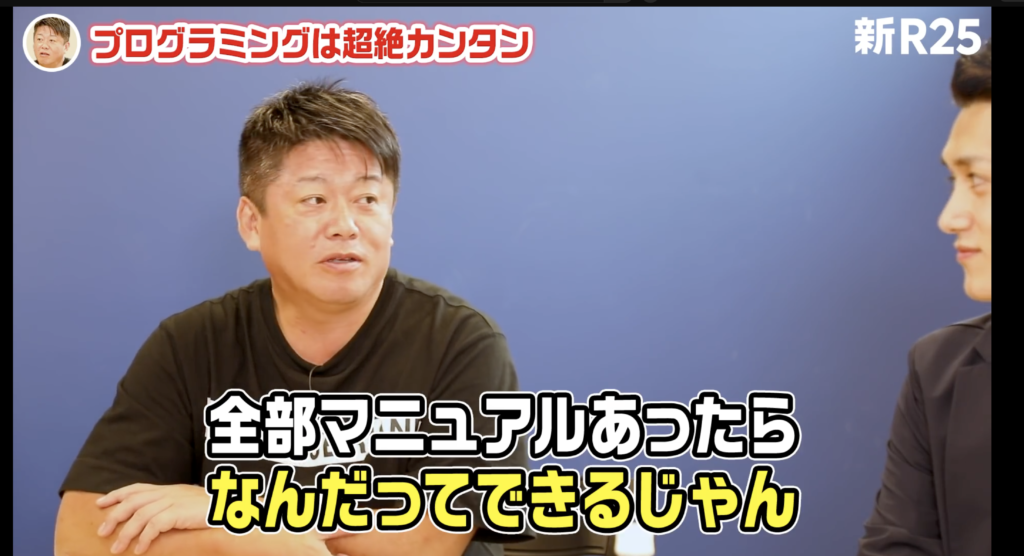
その恩恵に預かって、好奇心を満たし続けよう。

コメントを残す